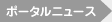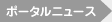|
2018.04.10 |
| ��w�N���ɎQ�����܂��B |
4���ɂȂ�A�܂����ĂȂ��r�N�g���[⤵
���ĂȂ����R�́A��������܂����A�A�A
���āA�������ɒ�w�N�̑��ɏo�ꂷ�邱�Ƃ����܂�܂����B
���iA��ł͏o�ꂷ��@��̖����I��������̗��K�̐��ʂ\���邱�Ƃ��o���܂��B
��w�N�A�F������Ă܂��B���ɂ͎�����K���Ă���q������ł��傤�B�w�͂��Ă���q������ł��傤🎵���̔��\�̏�ł��B
���A��w�N��A��ɏo�ꂵ�Ă���I�肪���܂��B
���������t��������܂��A�K�������ނ炪���̒�w�N�I��ȏ�ɓ����̎�����K��w�͂��Ă���Ƃ͌���Ȃ��B�B�B�B�܂�w�͂̌��ʂł��A������K�������ʂł��������Ă��ƁB(�ܘ_�w�͂��Ă���q�����܂���☺)
���̑I��Ɣ�ׂāA���͂������?���������B���͂������?�������肢�B�ƁA�������?�Z���X������B���Ă��ƁB������ƂĂ��厖�ʼn��l�̂��邱�ƁB�ł������Ƒ厖�Ȃ��Ƃ͍����荡���A������薾���B�ǂꂾ���w�͂����̂�?��肭�Ȃ邽�߂ɉ���������̂�?�ł��B
A��ɏo��o���Ȃ��I�肪�N������ԓw�͂��Ă��邩���m��܂����⚾
A��ɏo��o���Ȃ��I�肪�A�����ɏo�����ĒN����������K���Ă��邩���m��܂����⚾���̓w�͂̐��ʁA���̎�����K�̐��ʂ��������̑��ł����Ɍ��ʂƂ��Ă͌���Ȃ����Ƃ�����ł��傤�B
�ł��A���w�͂��Ă�����Ă���Ȃ�A�A�A�N������5�N���A6�N���ɂȂ����Ƃ��ɑ�ւ̉Ԃ��炩�����Ƃ��o����ł��傤🎵���͂����M���Ă���B
�����Ă����A��A��ɏo�ꂵ�Ă��āA���g�̃Z���X�ɊÂāA�w�͂��Ă��Ȃ��Ȃ�A�A�A������K�����Ă��Ȃ��Ȃ�A�A�A
��������̋͂��ȃZ���X�����Ŗ싅�𑱂����̂Ȃ�A�A�A�傫�ȉԂ��炩�����Ƃ��o���Ȃ��ł��傤❗(���������ƂA���݂܂���)
��w�N�̌N�����ցB
�싅�ɑ�����g�݂�l�����A�w�͂⎩����K�B�B�B
�������������Ƃ̐��ʂ͒����ɂ͌���܂���B�B�B
�ł��A�w�͂͗���܂���B
�N�����S�������w�N�ɂȂ����Ƃ��ɁA�A�A���̐��ʂ����ʂ��Č���邱�Ƃł��傤❗
�w�͂����q�́A�Ԃ��炩��🌷
�w�͂�ӂ����q�͉Ԃ��炩�����Ƃ��o���Ȃ��ł��傤❗
�S������ւ̉Ԃ��炩���Ă���邱�Ƃ����҂��A�M����Ƌ��ɁA���̂��߂̍ő���̎w����T�|�[�g�����邱�Ƃ����͖��܂��B |
|
2018.04.10 |
| ���Ȃ�������������A�ł��� |
�ȑO�A�~�X���ڗ�����s�����`�[�����������܂����B
�m���ɓ��e�̈��������������̂ł����E�E�ē��I��Ɍ��������t�ł��B�w���͂���Ȗ싅�͋����Ă��Ȃ��x�w���ɒp���������₪���āw���̊�ɓD��h��₪���āx�m���ɂ����������e�ł͂Ȃ��������ʂ��������Ǝv���̂ł����A���̓��e�͂������Ȃ��̂��ƁE�E
�ē���E�E���Ȃ��̂��߂Ɏq���͖싅������Ă���킯�ł͂���܂���B
���̌��t�����q���͂ǂ��v���̂ł��傤���H
�ē���ɒp���������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ���낤�ƂȂ�̂ł��傤���H����ȃ`�[����������̂͂��Ȃ��ł��B�m���Ƀ~�X�������Ȃ�A��s���i���܂����B
�ł����A�������������̂́w���Ȃ�������������ł���x�ƌ��������B���Ȃ��̎w���̎��������̌��ʂȂ�ł��B�m���Ɏq�����������Ȃ��Ȃ�������Ȃ����Ƃ���������ł��傤�B�ł��A���Ȃ������Ȃ��邱�Ƃ���������ł��傤�E�E�ƁB���̔��Ȃ��Ȃ��S�Ă��q���̂����ɂ��Ă��ẮA�w���҂Ƃ��Ă̐����͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�������ɂ����Ɠ{���Ă���l�A���܂���ˁE�E�E�悭�~�X�������Ȃ����肷��Ƌ������ăG�X�J���[�g����w���҂̕����������܂��B�w������Ă�[�I�Ă߂��I�x�w�����������Ă����܂ňꐶ�����Ă�I�x�w����Ȗ싅�͋����Ăˁ[��I�x�w���O�I������ĂI�o�J���I�I�x�ƂĂ�����鎶�B�ɂ͌������E�E���������ɔC���Ď����̊���ɔC���ē{���Ă��邾���̏�ԁB���������l���āE�E����̖ڂ��C�ɂȂ��Ă��傤���Ȃ���ł���ˁB
�w����ȃG���[����̃`�[���̎w���҂��Ǝv��ꂽ���Ȃ��B�x
�w���͂����Ƌ����Ă�̂ɂ����炪�o���Ȃ��B�x������A�w���ɒp���������₪���āx�Ȃ�Č��t�����C�ŏo�Ă���̂��Ǝv���܂��B
�܂��͍��̎����̎w���҂̖��n����F�߂邱�ƁB
����͎����̎コ��F�߂邱�Ƃɂ��Ȃ�܂��B
���̎コ�▢�n��������F�߂邱�Ƃ��o����E�C���K�v�Ȃ̂ł��B
��������X�^�[�g���Ȃ���A�����ƁA�q���̂����ɂ��Ă��܂��w���҂ɂȂ��Ă��܂��܂���B
�����āA�w���҂��q�ǂ������Ɋ|���錾�t�B
�u�o�J�v�u�^�R�v�u�}�k�P�v���̑��A�q�ǂ������J���錾�t�B
���蓾�Ȃ�❗ �w���҂́A�싅�̎w���҂ł���O�ɁA��l�ł���q�ǂ������̌��{�ƂȂ�Ȃ�������Ȃ��Ƃ������Ƃ����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�B�B |
|
2018.04.10 |
| �o�b�e���[�G���[ |
�`���p�`
�싅�ɂ�����\���i�ڂ��Ƃ��j�Ƃ́A�ߎ肪���ʂ̎���s�ׂɂ���Ď~�߂��菈�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��قǍ������A�Ⴗ���܂��͉��Ɉ���Ȃǂ�������̐��K�ȓ����̂��ƁB
����сA���̂��Ƃ������ő��҂�i�ۂ������ꍇ�ɕt��������L�^�B���C���h�s�b�`�Ƃ��ĂԁB
�������ߋ��\�ȃR�[�X�ɂ���Ȃ���ߎ肪�����ł����ɑ��҂̐i�ۂ��������ꍇ�͕߈�i�p�X�{�[���j�Ƃ���A�\���Ƃ͋�ʂ����B
�������A�������ߎ�ɒB����O�Ƀ����o�E���h���A���̌�̃{�[���̍s�����ߎ�̎���\�Ȕ͈͂ł������Ƃ��Ă��߈�ł͂Ȃ��\�����L�^�����
���A�\���ɂ�鑖�҂̐i�ۂ́A����̎��ӓ_�̗v�f�ƂȂ�i�߈�͂Ȃ�Ȃ��j
�`���p�I���`
�@�������ߎ�̑O�Ń����o�E���h����ƁA�߈�ł͂Ȃ��\�����L�^����܂��B���Ȃ킿�A�����o�E���h�̓�����ߎ肪�~�߂�ꂸ�A����ɂ���ă����i�[���i�ۂ��Ă��܂����ꍇ�A�L�^��͓���̉ߎ��ł���Ƃ��������ɂȂ�܂��B�������A���̈���Łu���ꂭ�炢�̃����o�E���h�͕ߎ�Ɏ~�߂Ăق����v�Ɗ����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��͂��ł��B�\���͕K����������̐ӔC�Ƃ͌������A���܂��ߎ肪���A�߈킾���łȂ��A�\���̐������点�邾�낤�Ƃ������Ƃł��B
�������A�����Ŋ��Ⴂ���Ȃ��ŗ~�����B�m���ɏ�肢�ߎ�Ȃ�\���̐��͌��点�邪�A���������\���𓊂��Ă��܂����Ƃɂ���肪����Ƃ������Ƃ��B
���Z����v���싅�œ���͑��ʂȕω�����p���Ă��܂��B
�T�C���͊�{�I�ɂ͕ߎ肪�o���Ă��܂��B
�Ⴆ�A̫���ްفB
��ײ��ް݂��缮�����ނ��邭�炢�̍����ɗ��Ƃ��B���̏ꍇ�A�ߎ�ͼ������ނ����邱�Ƃ�\�����\��/�߈�����O�ɖh�����Ƃ��ł���Ă���B
���Ė{��(?)
�L�^��ł͖\��/�߈�Ƌ�ʂ���邪�A����ő��̂Ƃ����ޯ�ذ�װ�ƌĂ�邱�Ƃ�����܂��B
�܂�A�L�^��̘b�ł��Ȃ��A�܂����̋L�^�̍����ƂȂ��Ԃł��Ȃ��A�\�����߈���ǂ�����ޯ�ذ�װ�œ���ɂ��ߎ�ɂ��ӔC������Ƃ������Ƃł��B
�\����������~�߂邱�Ƃ��o���Ȃ��ߎ�̐ӔC�ɂ��Ă͂����Ȃ����A�\���𓊎�̐ӔC�ɂ��Ă͂����Ȃ��B
�ޯ�ذ�װ�A�܂��ޯ�ذ(����ƕߎ�)��l�̐ӔC�ł���Ƃ������Ƃ����o�����Ȃ��ƁA������ߎ������Ƃ͖����ł��傤❗ |
|
2018.04.10 |
| �`�[���r�W����/���j(����) |
�`�����`
�Ⴆ�A�A�A
�u�l��A�I��������Ŏg���܂��BA�I��ȊO�̑I�肾���āA��������������͂��ł���B��������A�I��������Ɏg���܂��vC�R�[�`�͂����b���܂����B
�u�����͗��K�ŏo���Ȃ����Ƃ͎����ł͏o���Ȃ��ƌ��������Ă����B������A���̗��K���x��ł���A�I���厖�Ȏ����ł͋t�ɏo�����Ƃ͏o���Ȃ��v���Ȃ炻���b����ł��傤�B
�����āAB�R�[�`��A�I��ȊO�̑I�肪��Ԃƌ����܂������w���Ă����x���Ă��Ƃł͂Ȃ��Ǝ��̒��ł͎v���Ă����ł���ˁB
�u�������v���Ă����̂�����Ǝv���Ă��܂��B�����ƌ����u�������v���Ă����̂�����B
���ɂ��̑厖�Ȏ�����A�I����N�p���čŌ�ɃT���i���G���[�����Ă��܂����BA�I����[����������������܂���B���̎��ɂ����Ɨ��K�ɎQ�����Ă����悩�����Ǝv����������܂���B
�ł͎���̑I��͂ǂ��ł��傤�B
����A�I��ɉ��Ɛ����|����̂ł��傤���H
�w����������Ɨ��K�ɂ���悩�����x���t�ɏo���Ȃ��ɂ��Ă��S�̒��Ŏv���Ă��邱�Ƃ͂���͂��ł��B
�w�I�����x����ł�
���̎������ŏ㋉���Ƃ��čŌ�̑��Ƃ�����E�E
�^�ʖڂɗ��K�ɎQ�����Ă����I�肽���͂��́u�������v�ł͔[�����ďI���Ȃ���ł��B�����G���[��B�I�肪���Ă��܂��Ă��|�����鐺�͂���͂��ł��B�ꐶ�������K���Ă����p��m���Ă��邩��|�����鐺�������ł��B
�w�I�����x����Ȃ͂��ł��B
���K�ԓx�ł��������Ƃ������܂�
�����b�����ɂ���܂����A����͗��K���̑ԓx�⎩��������������ɂ���Ă���I����������Ƃ������܂��B
�m�b�N���Ƀ_���_�����Ă���I��A�o����̂ɂ�낤�Ƃ��Ȃ��I��E�E
�w�������x�w�������x�������Ă������Ƃ��w���҂̖��
�b�����ɖ߂��܂��ˁB
�������A�̑I��ɗ��K�ɗ���悤�A�ǂ����ė��K�ɗ���Ȃ����b�����܂����E�E���̏ꍇ�͂a�̑I��Ŏ����ɗՂ݂܂��B
���ꂪ�u�`�[�����j�v�ł���
���̕��j�Łu�`�[�����v�����Ă�������ł��B�N�ł��u���������v�Ǝv���Ă��܂��B
�ł����u�������v����ł��B
���̌��ʂƂ��āu�������v����Ȃ͂��ł��B
�����������Ƃ������Ă������Ƃ����N�싅�̎w���҂Ƃ��đ�Ȗ����Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���̂��߂ɂ̓`�[���r�W����/�`�[�����j�m�Ɏ������L���邱�Ƃ���ł��B |
|
2018.04.10 |
| �`�[���r�W����/���j |
�����K���x�ޑI���厖�Ȏ����ɏo���܂����H
�`�[���œ�l�̑I�肪���܂��B
���N�싅�̑I��N�p
�͂������Ă���̂ɋx�݂�����A�I��B�͂͗�邯�Lj������K���x�܂Ȃ�B�I��B
�����킪����܂��B
�Ă���|�W�V�����͈�B
�F����͂ǂ���̑I��������ŃX�^�����Ƃ��Ď����ɋN�p����ł��傤���H�����͂���܂��c
���ꂱ�����u�`�[�����j�v���ǂ��������̂��������Ƃ���ł��B
�ē�R�[�`���u���K���x�݂����ȑI��͎����ɂ͏o���Ȃ��v�ƌ��������Ă����̂ɑ厖�Ȍ����킾����Ƃ�����A�I����N�p�����B
����́u�����Ă邱�ƂƂ���Ă��邱�Ɓv���Ⴄ���ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B
�����u�����Ԃꂽ�v���ƂɂȂ�A�q���͕s�M�������A�e����͕s�����o�n�߂܂��B
�����߂Ɏ��͂�����I����o��
�ł́c�u���K�ɏo�Ă��Ă��o�Ă��Ȃ��Ă����͂�����I����g���v
����`�[���ł͊ēƃR�[�`���������������Ă���A�I��������Ŏg�����B�����ɘ_��������܂�����́u�`�[�����j�v�̂܂܂ł��B
���͂Ԃ�Ă��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�u�`�[�����j�v���w���҂͖��m�Ɏq���ɓ`���Ă����Ă���͂��ł��B
A�I��������ɏo����B�I��������ɏo�����͊e�`�[���̕��j�ɂ���ĕς���Ă���̂ł��B
�܂�A�q���B��
�u���������Ă������v����ł��B
�`�����`
|
|
2018.04.06 |
| Giant Killing (����2) |
�`�����`
�ł͊�Ղ��N�����\�����傫���`�[���Ƃ͂ǂ̂悤�ȃ`�[���Ȃ̂ł��傤���H
�݂�Ȃɉ��������`�[��
��Ղ��N�����`�[���͎���̐l�Ԃ𖡕��ɂ��܂��B
�ǂ�ȏ�ʂł��S�͎��������Ă���`�[���B
�S���爥�A�����Ă���`�[���B
���g�ɏΊ�Ő��������Ă���`�[���B
����͖싅�̎����̎������Ɍ���܂���B
�n�搴�|�����Ă���`�[������ł�����̎p�������n��̊F������������Ă���Ă���͂��ł��B
��������̉���������`�[���͊�Ղ��N�����\�����傫���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�X���[�K����O�ꂵ�Ă���`�[��
�F����̃`�[���ɂ��X���[�K��������Ǝv���܂��B
�S���싅�B
��ΌR�c�B
�s���s���B
���̃X���[�K���������̏���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��ł��傤���H
�ΐ쌧���̌�����Ő��ō��Z����t�]��������������܂����B
���ō��Z�̃X���[�K���́w��ΌR�c�x�����������ł��B
���̎�������ʃ��[�h���ꂽ�����ł��I�肽���́A�F�A�Ί�ł����B
�t���̎��ɂ����X���[�K����O�ꂵ�Ă���`�[������͊�Ղ��N�����\�����傫���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�O�Ղ��ɂ��Ă����`�[��
�w��Ձx���N�����`�[���ɂ͕K���w�O�Ձx������܂��B
�h�����K���݂�Ȃŏ��z���������O�ՁB
�싅�����߂����Ȓ��Ԃ��x���Ă����O�ՁB
�䂪�q���x���Ă����e�̋O�ՁB
�I���M�����Ă����w���҂̕��̋O�ՁB
�`�[���Ƃ��Ă�����Ă����O�Ղ�����`�[���͊�Ղ��N�����\�����傫���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
��Ղ͂��������N������̂ł͂���܂���B
�ł����E�E
��Ղ��N�����\�����傫���`�[���͕K������܂��B
����Ԃ��A�A�A
����O�Ղ��������ł́A��ՂȂ�ċN���Ȃ����Ă��ƁB�ł��B
|
|
2018.04.06 |
| Giant Killing |
GIANT KILLING
���̌��t�����������낤��???
�u�ԋ��킹�v�u�啨�H���v���Ӗ����錾�t�ł���A�X�|�[�c���Z�ɂ����āA���͍�������i��̑���ɑ��A�i�����������������ꍇ�Ɏg���B
�u�ԋ��킹�v
�ԋ��킹�i��킹�j�́A�\�����ʎ��Ԃɂ�蕨�����v�f�ǂ���ɐi�܂Ȃ��Ȃ邱�ƁA�܂��̓X�|�[�c�̎����Ȃǂɂ����Đ�͂�ߋ��̎��тŏ��鋣�Z�҂⋣�Z�`�[���ɑ��Ċi���ƌ��Ȃ���鑤���A���O�̗\�z���ď������邱�Ƃ��w�����t�ł���B���ɂ́u��Ձv�Ƃ܂ŕ\������邱�Ƃ�����B
�싅�ł����Ƃ��āw��Ձx�ƌĂ��o���邱�Ƃ��N����܂��B
���낢��ȏ�ʂŌ��I�ȃh���}�̂悤�Ȃ��Ƃ��N����܂��B
��ՂƂ��������́E�E
�W���C�A���g�L�����O���N�����Ձc
�ŏI��̑�t�]���c
��ՂƂ����͖̂{���N���邱�Ƃ��Ȃ����Ƃ��N���邱�Ƃ������܂��B
��ՂƂ������̂͂���ȂɊȒP�ɋN������̂ł͂���܂���B
������w��Ձx�ƌĂ�Ă����ł�����c
�������c
�w��Ձx�ƌĂ����̂��N�����`�[���ɂ͋��ʓ_������܂��B
��Ղ́w��x�Ƃ����������悭���Ă��������B�w�x�\�����w��x�����Ə����܂��B
�`�����`
|
|
2018.04.05 |
| �R���͂�肽���Ȃ�???(����) |
�`�����`
�R�������Ďq���Ƃ̋��ʓ_�����Ă�
�܂���́A�싅�Ƃ����q���Ƃ̋��ʓ_�����Ă����ƁB
�u�싅�̋Z�p�v���q���ɋ����邱�Ƃ͏o���Ȃ����������
�u�싅�̃��[���v���q���ɋ����邱�Ƃ��ł��܂����B
������Ă������厖�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B
�R�������Ă�������̐l�ƒ��ǂ��Ȃꂽ
��ڂ́A�R�������邱�Ƃł�������̐l�ƒ��ǂ��Ȃꂽ���ƁB
�싅��S���m��Ȃ����������R����ʂ��Ă�������̐l�ƒm�荇�����ǂ��Ȃ�܂����B
�q�����`�[����ޒc������������ƒ��ǂ������Ă�����č��ł��u�R���k�`�v�ɉԂ��炫�܂��B
������q�����싅�����Ă���Ă��������ł��ˁB
�q���̃v���[���ԋ߂Ō��ꂽ
�O�ڂ́A�q���̃v���[���ԋ߂Ō��ꂽ���ƁB
�O���E���h�̊O���猩��q���ƃO���E���h�̒��̎q���͑S���Ⴄ�q�Ɍ����܂����B
�s�b�`���[�ɑ��鐺�̂������B
���������ȕ\��B
�O���E���h�̒��ɂ������炱���킩�������Ƃ���������܂����B
�G���[�������Ƃ��͌�납��R����������Ȃ�܂������ǁi�j
���e�Ƃ��ĕK���̎p�������ꂽ
�l�߂́A�q���̐g�߂œw�͂���p�������ꂽ���ƁB
�R�������ƌ��߂Ă���͕K���ɕ����܂����B����̐l�ɂ��悭�{���܂����i�j
���̎p���q���Ɍ�����͍̂ŏ��͒�R������܂�����B
�u��������邢��������v
�Ɖ䂪�q�ɉf���Ă���낤�Ȃ��ƁB
�����A���߂����Ǝv�����Ƃ�����܂������E�E
����ł��A�����o�����ɑ����܂����B�p�������Ȃ��炩���������p���q���Ɍ����邱�Ƃ��E�E
���e�Ƃ��āu�������������Ɓv�Ȃ�Ȃ����ȂƎv���n�߂���ł���B������A�q�����p�������Ƃ��������Ă�
�u������ȁI�v
�Ǝ����������ƂŐ����͂��o���Ȃ����ȂƁE�E
�����v���Ă��܂��B
��肽���Ȃ�����肽������肪����
�R���ƕ����Ɓu��肽���h�v�Ɓu��肽���Ȃ��h�v�ɕ�����Ă��܂������ł��B
�ł�����x���n�߂��
�u��肽���Ȃ��h�v
����������������
�u��肽���h�v
�ɕς��
�u��肪���h�v
�ɂȂ邱�Ƃ���������܂��B
���A�R�����u��肽���Ȃ��h�v�̂�������E�E
������Ƃ����E�C�Ől���̂�肪�����������邩������܂����
�`���p�I���` |
|
2018.04.05 |
| �R���͂�肽���Ȃ�??? |
�R������肽���Ȃ��Ƃ����O�ɓǂ�ł�����������
�`���p�`
���N�싅��N���u�`�[���̂�������̎d���̈�Ɂw�R���x������܂��B
�u�ł����肽���Ȃ��I�v
�u���ŃI�����I�v
�u�R���Ȃł��Ȃ��I�v
�{�S�͂���Ȋ�����������܂���B
�싅���킩��Ȃ����炱���R�����E�E���̃`�[���ɂ����c����ۂɁu�R���ł��Ȃ��̂ł������Ȃ�������܂��H�v
������������邨���l����������Ⴂ�܂��B
�q������������Ƃ���
�u�R������肽���I�v�Ǝv���Ă���l�̂ق������Ȃ��ł���ˁi�j
���̃`�[���ŐR��������Ă����������قƂ�ǂ̂����l���u�싅���o���v�̕��ł��B
������u�싅���킩��Ȃ�����R�����ł��Ȃ��v�Ƃ�������������������Ⴂ�܂��B
�ł����A�t�Ɂu�싅���킩��Ȃ���������悤�v�Ǝv���Ă������������������Ⴂ�܂��B
����A��������R���̋L�������������Ƙb������A�̃`�[���ɍݐЂ��Ă������������ɘb���Ă��ꂽ���Ƃł��B
���̕����싅���o���ł������R�������ėǂ������ƌ����Ă��������܂����B
�ƂĂ��Q�l�ɂȂ邨�b���Ǝv���܂��̂ł��ǂ݂�����������Ǝv���܂��B
�`�����` |
|
2018.04.04 |
| �ēA�R�[�`���{�闝�R??? |
���N�싅�̊ēE�R�[�`�͂Ȃ��{��̂�?
���N�싅�̊ēE�R�[�`�͓{�炸�ɂ����Ȃ��̂ł��傤���H
����Ȍ��t�����ɂ��܂��B
�_�߂邱�Ƃ��ǂ��Ƃ���鎞��ł����q�������邱�Ƃ��K�v���Ǝ��͍l���Ă��܂��B
������@�`�B�̎w���҂̓{���������܂������̂R�ɂ͂��鋤�ʓ_������܂��B
�@�����̋C���œ{��ēE�R�[�`
�ƒ���Ђʼn����������̂ł��傤���H
�Ǝ��肪�v�����炢�{��ēE�R�[�`����������Ⴂ�܂��B
�{���Ă���q�����������œ{���Ă���̂����R���킩�炸�E�E�E
�C�����ƌĂ��l���w���҂ɂ���Ǝ��肪��ςɂȂ�܂��B
�����̋@����C���œ{���Ă͎q�������܂������̂ł͂���܂���B
�A���������Ƃ��ł��Ȃ�����{��ēE�R�[�`
�w���킹��I�x
�w���x�������o�����I�x
���������������Ƃ��o���Ȃ��c
������{��B
�o����E�o���Ȃ��ł͂Ȃ��c
��낤�Ƃ��Ă��邩�ǂ�������Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�o���Ȃ��͎̂q���ł͂Ȃ������̎w���͂ɖ�肪�������̂�������Ȃ��Ǝ~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��ēE�R�[�`���w�q�����o���Ȃ��x���Ƃɂ������ē{���Ă��܂��܂��B
�B����̖ڂ��C�ɂ��ē{��ēE�R�[�`
���͑����̂����̃p�^�[���ł��B
�������Ɏq�����G���[������B
�~�X������B����`�[���̊ēE�R�[�`�Ɏ����̔Ȃ����Ƃ��A�s�[�����邩�̂悤��
�w���͂���Ȗ싅�������Ă��Ȃ��x
�����{��w���҂���������Ⴂ�܂��B
������āc�q�����Ă܂��ˁH
�����ɂ͔Ȃ��c
�����Ă���̂ɏo���Ȃ��R�C�c�炪�����B���͖싅��m���Ă���B
���͂����Ƌ����Ă���B
����̖ڂ��C�ɂȂ��Ă������Ȃ��̂ł��B
�{��Ǝ���
�@�`�B�̋��ʓ_�c
���C�t���ɂȂ�ꂽ�ł��傤���H
���S���q���ł͂Ȃ��c
�����Ȃ�ł���ˁB
�����̌��������悤�Ɂc
����Ȃ��ƋC���ς܂Ȃ�����c
���́w�{��x�Ƃ�������́c
�q���̐S�ɓ͂��̂ł��傤���H
�q���̂��߂�z���āc
�q���ɓ`���悤�ɘb�����Ƃ́c
�w�{��x�ł͂Ȃ�
�w����x�ɂȂ�܂��B
�������N�싅�̌���ɂ���Ǝq���������Ŏ����邱�Ƃ�����܂��B
�S�͎�����ӂ����E�E
���ԂɐS�������t���������E�E
�e�䂳��̗��ꂩ�炷��Ɖ��́w�����Ă���x�̂����������茩�ɂ߂邱�Ƃ���ł��B
|
|
2018.03.30 |
| �O���E���h�����ɂ��āB(����2) |
�O���E���h�����͒N������̂��H
�������N�싅�����Ă��āA�^��Ɏv���Ă��鎖�B
�E�Ȃ��A�O���E���h�������l������Ă���̂��H
�E�O���E���h���g���I�肪��������̂�������O�ł͂Ȃ��̂��H
���͗c��������싅������Ă��܂������A�]���̑���v�����g������ȊO�őI��ȊO�̐l���O���E���h���������鎖�͂܂�����܂���ł����B
���́A�w�ǂ̏��N�싅�`�[�����O���E���h�����͑�l�i�ē@�R�[�`�@���Z�j������Ă���Ǝv���܂��B��x�A�m�F������������܂����B
�Ȃ��A�q���B�ɃO���E���h�����������Ȃ��̂ł����H
�����������A����ȉ����܂����B
�E�O���E���h�̎g�p���Ԃ����܂��Ă��邩��A���Ԃ��ܑ̖��������l������ł��B
�E�̂������Ă���̂ŁA�p�����Ă��܂��B
�E�q�������ɐ���������ƁA���܂ł����Ă��I���Ȃ���ł���B
�ƁB�B
���A�l�̍l���́u��Ɏg���{�l�B�ɃO���E���h�����͂�����K�v������v�Ǝv���܂����A�����͕ʂł��B�����J�n���Ԃ����܂��Ă���̂ŁA����ɍ��킹�Đg�̂ƐS�̏���������K�v�����邩�炾�Ǝ��͎v���Ă��܂��B
�Ȃ��A�I�肪�O���E���h��������K�v������̂�?
�����������g�����O���E���h�����̕����C�����ǂ��g���Ă��炤�ׁB
�������������ꂩ��g���O���E���h�ʼn����~�X�����Ȃ��ׁB
�����l����ƁA�g���I��A�g�����I�肪�O���E���h����������̂����R���Ǝv���܂��B
���ӂ̋C�����ł��B
���K���Ԃ̓O���E���h�������܂߂����Ԃł��B
�O���E���h���������ł͂Ȃ��A����̏�������Еt���A�O���E���h�������K���ԂɊ܂߁A�w�Ԃׂ������Ǝv���܂��B
�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�r�N�g���[�ɂ����Ă��O���E���h��肩��O���E���h�����A����̏���/�^��/�Еt����I��ɂ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
�R�[�`�A���Z�̕��X�͎��炪�����̂ł͖����A�I�肽�������悤�ɐ����Ē����܂��悤���肢�������܂��B�B |
|
2018.03.29 |
| �ߋ��̎v���́A�ς����� |
�ߋ��͕ς����Ȃ��ƌ����܂��B
�����̃G���[�ŕ����Ă��܂��������B
���́A���̎��A�߂�Ȃ������̂��낤�Ɨ����������܁B
��������Ă����ߋ��E�E
�싅�����߂����Ǝv�����ߋ��E�E
�������ł��Ă���Ώ��Ă������B
���́A���̎��A�łĂȂ������̂��낤�Ɨ����������܁B
�m���ɋN�����Ă��܂����ߋ��͕ς����Ȃ���������܂���B
�ł����A�ߋ��ɋN���������̎v���͕ς�����͂��ł��B
���ꂾ���������v���������̂Ȃ�E
���ꂾ�����̃G���[���������̂Ȃ�A���̈ꋅ��߂邽�߂ɉ�����̋���߂邵���Ȃ��B
���ꂾ�����̈�ŐȂ��������̂Ȃ�A���̈�ŐȂ̂��߂ɉ�������o�b�g��U�邵���Ȃ��B
�G���[���O�U�������Ė싅�ł��B
���̓����E�E
���̉��������E�E
���̓������������炪��ꂽ�Ƃ����ߋ��ɕς��Ă��������B
�����̎��������Ă��܂��B
������w���x������邵���Ȃ���ł��B
�����炱���A���̓��A�����������̂Ȃ�A���������ė~������ł��B
�{���{�������������B
���܂͐h���ł����q�����傫���ς��`�����X�ł��B
�ߋ��̏o�����͕ς����Ȃ����ǁA��������邱�Ƃɂ���āA�ߋ��̎v���͕ς�����͂��ł��B |
|
2018.03.27 |
| ���� |
30�N�ȏ���O�̘b�B
���͖싅���n�߂܂����B
���w�Z3�N���̏t�B
�����������Ă����`�[���ł́A
6�N����A�`�[��
5�N����B�`�[��
�ƌ��܂��Ă��܂����B
4�N����C�`�[���̑��������A3�N���ȉ��̃I�����W�{�[����
����܂���ł����B
�����͂܂�?�싅�l�C�ň�w�N��10�l�ȏア�܂����B
3�N���t����ꏏ�ɓ�������������7�l�B
�����j���O�A�̑��A�L���b�`�{�[���B
�����܂ł́A5,6�N���Ɠ������K���j���[�B
��������́A������K��o�b�e�B���O���K���n�܂�̂ł����B
�w���҂����Ȃ��A�O���E���h�������A�A�A
3,4�N���́A�����j���O�A�f�U��A�V�[�g�m�b�N�̃����i�[����ȗ��K���j���[�B
�{�[�����g�������K��3,4�N���͈���Ȃ��B
����ȃ`�[���ł����B
�w���҂��ق�Ə��Ȃ��Ƃ��́A�����j���O���炵�Ȃ��B
1��ɕ���łЂ����琺�����B
�������N���ăO���E���h�ɍs�����̂́A�����j���O�A�̑��A�L���b�`�{�[���̂��Ƃ͗��K���I���܂ł����Ɛ������B����Ȃ��Ƃ��p�ɂɂ���܂����B
�����������Ɛ�y������w���҂�����{���A�A
�싅����肽���ē������̂ɁA�A�A���āB
�ł����̔������炩?�A�Ƃł͑f�U�肵����A�Ǔ��Ă�����A�F�B�ƃL���b�`�{�[��������A�A�A�����ł����܂��Ȃ�A���w�N�̗��K�ɍ����Ă��炦��̂������ĒW�����҂�����Ȃ���B�B�B
����B��w�N�̑���I�����W�{�[��������A
�`�[�������o�[�����Ȃ��ƍ��w�N�̎����ɂ��o�邱�Ƃ��o����B
�A�܂�����������B
�ƁA�����ɒ��w�A���Z�Ɛi�Ƃ���
�`�[�����̐킢�ɏ��Ă�̂��Ȃ��Ƃ��B
�w�͂��Ȃ��Ō���(�����ɏo��)���o��Ɩ��S�ɂȂ�B
�w�͂��Č���(�����ɏo��)���o��Ǝ��M�ɂȂ�B
�w�͂��Č��ʂ��o�Ȃ��Ă��o�����c��B
�w�͂��Ȃ��ŁA���ʂ��o�Ȃ���Ό�����c��B
�w�͂́A�R�����Ȃ�❗
�싅����肢�A����Ȃ�ĊW�Ȃ��B
�厖�Ȃ̂͏�肭�Ȃ������ǂ���?
�����o�����̂��ǂ���?
�싅��������Ȃ��B
�ǂ�Ȃ��Ƃɂ����Ă��w�͂������邱�Ƃ��o�����l�ɂȂ��Ăق����A�Ɗ肤�B |
|
2018.03.26 |
| �S���{�]�ː���� |
�s�m���t���]�\�I(�������ʎQ��)����1�T�ԁB
�S���{�]�ː����1���⚾
���j���ɐႪ�~�����Ƃ͎v���Ȃ����V☀
�싅���a�̒��A�J���1��킪�s���܂����B
(���ʂɂ��Ă͎������ʎQ��)
�����͂������̂́A1�_���ɔ������Ƃ��̑I�肽���A�x���`�̕��͋C�͗ǂ�����❗
�I�肽������ɂȂ��Ă���悤�ȋC�������B
�~�X���������B������⤵
���A���������ł����B
�ۑ肪�͂�����ƌ������A����Ȏ����ł����B
�������A�������ł͂��邯��ǁA�I�肽���͐������Ă��܂��B
�l�l�̓w�͂ƁA�`�[�����K�ł̏W���͂��A����̏����ւƓ����Ă����ƐM���Ă��܂��B
����̊F�l�A��������̉������肪�Ƃ��������܂���🙇
���Ӓv���܂��B
|
|
2018.03.22 |
| ���Ǝ�(�吙��Q���w�Z) |
�y���A�����A�I���A����l�A���āA�D��A�nj�B
���Ƃ��߂łƂ�✋
�����Z�̊F�l�A��q���̂����Ɛ��ɂ��߂łƂ��������܂�⤴
4������͒��w��✏
�d���Ŗ싅�𑱂���q�B
��Ŗ싅�𑱂���q�B
�V���ȃX�|�[�c�Ƀ`�������W����q�B
�V��������ɖ������߂�q�B
���w�Z�����̎v���o�ƁA�r�N�g���[�ł̎v���o��
�Y��邱�ƂȂ��A���w�ł̐V�������Ɍ������Đ���t�`�������W��
����݂͂Ƃ��Ă��������B
�������Ă��܂��B
�N�������������āA�r�N�g���[�ɗV�тɗ��Ă��̎p��
�����ɗ��Ă��ꂽ��ƂĂ��������ł��B
�撣��👊😆🎵 �y��
�撣��👊😆🎵 ����
�撣��👊😆🎵 �I��
�撣��👊😆🎵 ����l
�撣��👊😆🎵 ����
�撣��👊😆🎵 �D��
�撣��👊😆🎵 �nj�
|
|
2018.03.21 |
| 3��21�� �t���̓� ��⛄ |
�s���ł����̊J�Ԃ���N��菭�������錾����A
�t���������������܂ł���ė��Ă���̂��ȁH
�ƁA�v���Ă����̂ł����A
�܂����̐�⛄
����🌁⛄🌁
�̒�������Ă��܂��\��������̂�
���K����ӂ̎��_�ő��X�̒��~�ɁB
�T�b�J�[⚽��O�r�[🏈�́A�J�ł�
��ł����̂ł��傤���ˁB�B�B
�v���싅�̋�����h�[�����̋��ꂪ�����A�J�ł��W�Ȃ�
�������s���܂�⚾
�w���싅�ɂ����Ă�
�����r���ɉJ���~�邱�Ƃ�����A
�Ⴊ�~�邱�Ƃ����蓾�܂��B
���J���x�Ȃ�A�����͑��s����邵
�����̃O���E���h�s�ǂł����������{�����
���Ƃ�����ł��傤�B�B�B
�̒�������Ă��܂��ƌ����q���Ȃ��ł����A
�g�����J�̓��Ȃ�A�J�V���̎�����z�肵��
���K����̂��悢�̂�������܂���B
|
|
2018.03.14 |
| �����t�@���R���Y��(3/18) |
���悢�捡�T���̓��j���ɁA�s�m���t�]�ː���o�������������������܂��B
�����̗��K�̐��ʂ�����Ώ��Ă܂��B
���Č��������Ƃ���ł����A�ΐ킷�鏼���t�@���R���Y�Ƃ̗͂̍��́A�A�A
��������܂��B
�����t�@���R���Y�́A���N���Ɍ�������܂߂�15�����ȏ���{���Ă��܂��B
�吙�r�N�g���[��4�����B
�����̐��̍��ł͂Ȃ��B�V�`�[���n�����Ɏ������o����̐����������ۂ��̍��ł��B
�Z�p�I�ȍ����ܘ_����܂��B
�����������A
�����������A�ł��B
���ĂȂ���ł͖����B
���������ɑ厖�B
���ĂȂ���ł͖�����ł��B
�ȒP�ɂ͏��ĂȂ��B�ł��A�A�A�B
����`�ǂ�����̂�?
������������Ɗ撣��B
���₢��A�}�ɏ�肭�͂Ȃ�Ȃ���💦
����`�ǂ�����?
���͏��Ƃ����C�����B�����S�B
�Ō�̍Ō�܂ŁA�싅(����)�ɐ^���Ɏ��g�߂邩�ǂ����H����
�v���Ă��܂��B
��������A�����̐��ʂ��\�ɔ������邱�Ƃ��o����Ƌ��ɁA
���Ă�m�������������܂��Ă���͂�����❗
�܂��܂��r�N�g���[�̑I��͔��W�r��B
�ł��A�ŏ�������키������߂��Ƃ�����A�r���Œ��߂��Ȃ珟���̏��_�͈�ؔ��ނ��Ƃ͖����ł��傤❗
|
|
2018.03.14 |
| �ڂ����Ęb���B�ڂ����ĕ����B |
~�ڂ����Ďq���̘b���Ă��܂����H
�w�l�̘b�͖ڂ����Ē����Ȃ����x
�w�l�ɘb���Ƃ��͑���̖ڂ����Ęb���Ȃ����x
�`�[�����C�g��q���Ǝw���҂̊ԂŃR�~���j�P�[�V���������Ƃ��Ɋ����Č��Ō���Ȃ��Ă��ڂ�����Ό����������Ƃ��킩��Ƃ����t�������ڂ������ق����{�S���킩��Ƃ����Ӗ��ł��B
�l�ɉ����b�����E�E
�l�̖ڂ����Ęb�����ƂŁw�`����́x�������Ȃ�Ǝv����ł��ˁB
�l�̖ڂ����Ęb�����Ƃ�
�����q���ɘb������Ƃ��K���ڂ����Ęb���A�q�����b������Ƃ��͖ڂ����Ē����悤�ɂ��Ă��܂��B
������̓`���������Ƃ������ł��`���悤�ɂƁE�E�����炪�������������āu�͂��v�ƕԎ������Ă��ڂ��݂�Ɓu���[�R�C�c�킩���ĂȂ��ȁv���Ă���������܂���ˁB�B
����͖ڂ����Ă��邩��킩�邱�Ƃ��Ǝv���̂ł��B
�w������Ă�����A�{��ꂽ�肵�Ă���Ƃ��ɉ��������āA�ڂ������Ȃ��q�ǂ����������܂��B
����́A�킩���Ă��Ȃ����Ƃ�����Ȃ��悤�ɂ��Ă���̂ł��B
��X��l���E�E
���X�q���̊�����Ȃ��œK���Ȉ��A��������c�q�����ē�R�[�`�ɘb�����ɍs���Ɓw���[�킩�����킩�����x�ȂǂƊ�����Ȃ��Ō��t��Ԃ��l�����܂�������ł͎q���̐S���킩��Ȃ��Ǝv���̂ł��B
�����g���C�����Ȃ�������Ȃ��̂ł����E�E
���̃o�^�o�^���Ă��鎞�ԂɃX�^�b�t���m�Řb�����������Ă���Ƃ���
�q�������A�����Ă���Ă���̂Ɏ��Ԃ��Ȃ�����v�킸�ڂ����Ȃ��Łw���͂悤�x�ƕԂ��Ă��܂���������܂��B
�A�C�R���^�N�g�̓v���[�ɂ��o�Ă��܂�
�v���[���Ɂu�A�C�R���^�N�g�v�𒇊ԓ��m�ł���ꍇ������܂��B
�싅�͂�����ƃ{�f�B�A�N�V�����Ŏw�����o���m�F�������X�|�[�c�ł����E�E
�ӊO�Ɂw�ځx�ʼn�b�������ʂ������̂ł��B
�������ł��c
���퐶���ł��G���x�[�^�[��҂��Ă����E�E�ǂ��炪��ɏ�邩��m��Ȃ��l�Ɩڂ������ăj�R�b�Ƃ��Ă���w�ǂ����x
�Ƃ����悤�Ȏ�������܂��B
�ڂ��������炱��������ʂł��C�������悭�Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�S�̒��͌����܂��c
���̐S�������Ă����̂��u�ځv�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�ڂ����Ęb�����Ɓc
�ڂ����Ęb�����邱�Ɓc
��l���q���Ɍ����Ă������邱�ƂȂ̂��Ǝv���܂��B
|
|
2018.03.14 |
| �L���b�`�{�[���͑��(����) |
�`�����`
�R�@��b�̃L���b�`�{�[�����o����悤�ɂȂ�
�L���b�`�{�[�������Ă���Ƃ���
�w���[�I�i�C�X�{�[���I�x
�w���[�I�T���L���[�I�x
����Ȃ���肪�ł��Ă����
�w���t�̃L���b�`�{�[���x���ł��Ă���؋��ł��B
�w���O�ǂ��ɓ����Ă�I�x�ȂǂƎ����̊�������Ԃ��Ă��܂��Ă���̂̓L���b�`�{�[���ɂȂ�܂���B
�L���b�`�{�[���̓{�[�������łȂ����t�ł��o������̂ł��B
�����āw���t�̃L���b�`�{�[���x�̓v���[�ɂ��������ɂ��q�����Ă��܂��B
�S�@�L���b�`�{�[���Ŏ�����m��
�L���b�`�{�[��������ƍ����̎����̏�Ԃ��킩��܂��B
�w����E�E�����͂Ȃ������d�����x
�w����E�E��]���������x
���̂悤�Ɏ����Ŏ����̒��q���L���b�`�{�[���ł킩��悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�����Ă��̎����̏�Ԃ�m�邱�Ƃɂ���ăL���b�`�{�[�����ǂ̂悤�ɂ����炢�����l����悤�ɂȂ��Ă��܂��B
��]��������Ύw�̂�������ӎ����ē�����悤�ɍl���Ă����킯�ł��B���̓��̎����̏�Ԃ��L���b�`�{�[���ł킩��q�͎��ȊǗ����o���Ă���q�ł��B
���̂̓{�[����������Ȃ�
�L���b�`�{�[���́w�L���b�`�x�Ƃ����͕̂����ʂ�w���x�Ƃ����Ӗ��ł��B
����̑z���⌾�t���w�L���b�`�x����̂ł��B
���̑z���⌾�t�𔒋��ɍ��߂�̂ł��B
�L���b�`�{�[���͋Z�p�����ł͂Ȃ��l�Ԍ`����m���ł�����܂��B
�q�ǂ������́A�\��������/�\�����ꂽ�����ɂǂ̂悤�Ȍ��t��ɂ����Ă���ł��傤���ˁB�B�B |
|
2018.03.14 |
| �L���b�`�{�[���͑�� |
�`�L���b�`�{�[������ȗ��R�`
�L���b�`�{�[���͑���ƌ����܂��B�L���b�`�{�[���͑S�Ă̊�{�ɂȂ�܂�����ƂĂ���ł��B
�L���b�`�{�[���Ƃ����v���[�͋Z�p�I�Ȃ��ƈȊO�ɂ���Ȃ��Ƃ����͂�������܂��B
�L���b�`�{�[�����l�Ԉ琬�̂��߂ɂȂ��Ă���S�̂��Ƃ������Ă݂����Ǝv���܂��B
1�@�L���b�`�{�[���͐S�z�肪�o����悤�ɂȂ�
�L���b�`�{�[���ɃG���[�Ɩ\���͂����̂ł��B
�\�������Ă��܂���
�w���߂�I�x�Ǝӂ�B
�����Ė\���������{�[����ǂ������悤�Ƃ���Ƒ��肪
�w������I������I�x
�Ƒ����ă{�[����ǂ������Ă����B�\�������ق������ꂽ�ق����E�E
��������đ���Ɂw�S�z��x���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�����āA���������w�S�z��x�̓v���[�ɂ��������ɂ��q�����Ă��܂��B
�ł�����A���̓L���b�`�{�[���̎��ɑ�l�����Ń{�[���E�������邱������f�肳���Ă��������Ă��܂��B
��l�����E�������Ă��܂��̂͗��K���Ԃ�Z�k���������Ȃ�����Ȃ̂�������܂���B
�ł����\��������G���[�������肵���{�[���𑖂��Ēǂ������邱�Ƃ����K�̈�ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����āA��l�����E�������邱�Ƃɂ���Ďq���́w�C�t���̃`�����X�x��D���Ă���̂�������܂���B
�Q�@�L���b�`�{�[���͐S�z�肪�o����悤�ɂȂ��Ă���
�w�L���b�`�{�[���͑���̂��Ƃ�z���ē����Ȃ����x
�Ƃ悭�����܂��B
�w����̂��Ƃ�z���ē�����x�Ƃ������Ƃ͂�邢�{�[���𓊂��邱�Ƃł͂���܂���B
���肪�߂�₷���Ƃ������Ƃ͎��̓���ł���w�����₷���{�[���x�𓊂��Ă����邱�Ƃł��B
���ꂪ����ɑ��Ắw�z������x�ł��B
���̑z�����肪�v���[�ɂ��������ɂ��q�����Ă��܂��B
�`�����` |